ICEBA(アイセバ/生物の多様性を育む農業国際会議)は、生物多様性を基盤とした地域循環型農業技術の確立と、国内外への普及を目指す国際会議です。2025年7月12日・13日には、7回目となるICEBA7が徳島県小松島市で開催されました。
2025年7月13日、分科会④では、これまでのICEBA開催地から、生物の多様性を育む農業を中心軸とした各地の取り組みが報告され、ICEBAの成果や地域の課題、未来への展望が共有されました。

連携して生物多様性農業に取り組む ~徳島県小松島市~
2010年に発足した生物多様性農業推進協議会を中心にJA東とくしま、コープ自然派、NPO法人とくしま有機農業サポートセンターなどが連携し、地元資源を活用した循環型農業を推進し、担い手育成や有機栽培技術講習を行っています。「オーガニック・エコフェスタ」を通して消費者や地域の理解を広げて農業の魅力を発信。学校と連携して生物多様性フィールド講座などを開催し、給食に有機農産物を提供しています。
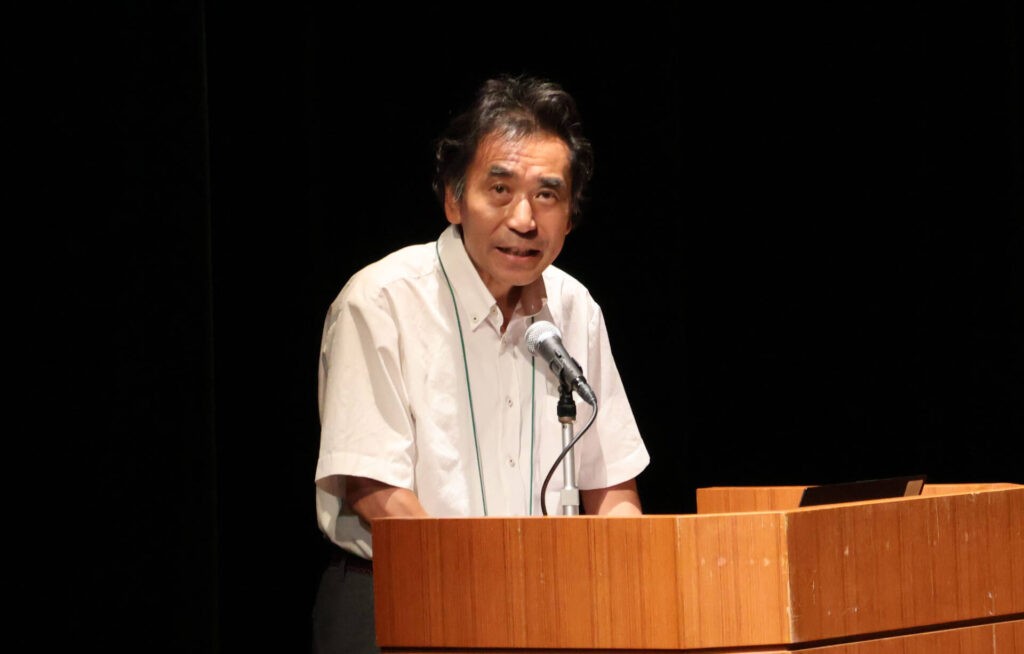
コウノトリと米づくり ~兵庫県豊岡市~
第1回ICEBAの開催地である豊岡市では、安全な農産物と生きものを同時に育む「コウノトリ育む農法」を確立しました。子どもたちは「お米を食べるとこの農法の田んぼが増え、生きものがいきいき暮らせる自然環境が増える」と市長に直談判し、2007年から給食に導入。全量無農薬米の給食をめざして栽培面積を拡大しています。農家は「子どもたちに一番安心なお米を」と栽培に取り組み、理念を継承するため「コウノトリ育むフォーラム」も計画中です。

ICEBAが育んだ誇り ~新潟県佐渡市~
2011年、世界農業遺産に認定された佐渡市は「トキと共生する佐渡の里山」を掲げています。生きものと環境への配慮を優先した農業でトキは増えましたが、担い手不足が課題です。お米・里山・生物多様性の価値を守るために、市独自の認証制度や子どもたちへの食育のほか、各課が連携して食べることで農業を支える取り組みを進めています。

田んぼがつなぐ浮世絵の風景 ~宮崎県大崎市~
ラムサール条約湿地に登録される国内最大級のマガンの越冬地・蕪栗沼の周辺で「冬水田んぼ」に取り組んでいます。田んぼの生きものを健康診断のようにモニタリングし、農家の気づきや工夫を広げます。こうしたデータを生物多様性の再構築や認証米の販路拡大に活かすことが、今後の大きな課題です。

田園環境都市おやま ~栃木県小山市~
ラムサール条約の理念に基づいて渡良瀬遊水地の周辺で冬水・夏水田んぼの活用と保全を進め、コウノトリの野外繁殖に6年連続成功しています。コウノトリが日常的にいる景色を子どもたちの未来に残すために有機農業に取り組み、有機農業取り組み面積は2025年には30 haを超える見込みです。公共調達を最優先で考え、4年後には市内小中学校の給食米の全量有機化を目指しています。
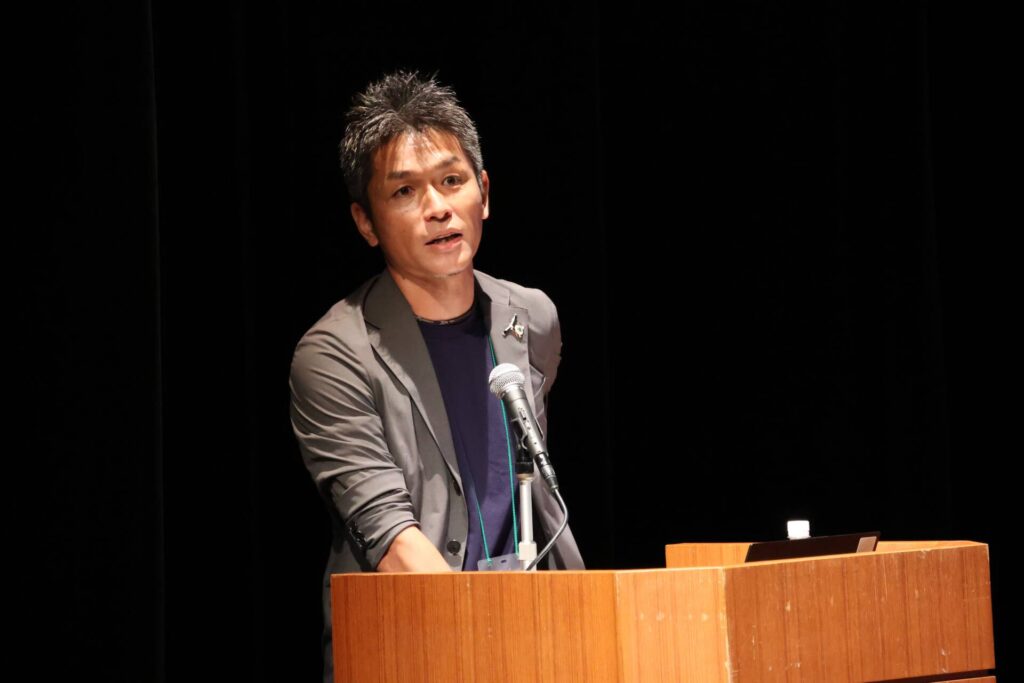
自然と共生する里づくり ~千葉県いすみ市~
いすみ市の有機農業推進は、2012年「自然と共生する里づくり連絡協議会」の発足が発端でした。農業部会と環境部会が両輪となり、生物多様性に根ざした地域づくりを推進。2017年には全国初の学校給食米100%有機化を達成しました。2018年から有機野菜も導入。教育ファームや食育授業を展開し、子どもたちが将来「地域を支える消費者」となることを目標に公共調達の拡大に取り組んでいます。

とくしまコウノトリ基金 ~徳島県~
2019年設立。コウノトリの定着・繁殖と、自然と共生する農業・地域活性化をめざしています。耕作放棄地のビオトープ化やれんこん畑の活用が進み、「コウノトリレンコン」や、鳴門市に定着したコウノトリ「アサヒ」「ユウヒ」にちなむ地酒「朝と夕」、味噌などの商品も誕生。消費者の購入が環境整備につながっています。農業体験や環境学習も実施され、次世代への理解も広がっています。
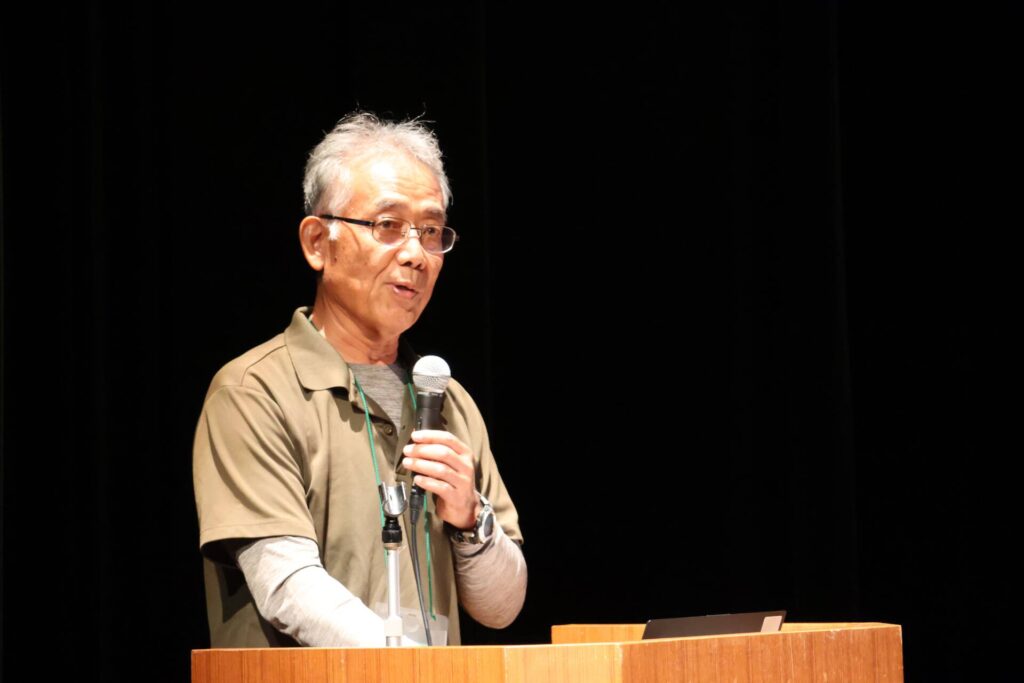
生物多様性は暮らしと未来を支える基盤です。生物多様性農業は地域の資源を循環させる取り組みでもあり、異常気象や社会的課題にも強い持続可能な社会を築く力となります。技術習得や担い手不足、経営課題はありますが、農家・行政・消費者が協力することで、豊かな地域と生きものの命を次世代に受け渡すことができます。座長の呉地さんは「ICEBAはその思いを共有し、未来へとつなげる大切な議論の場です。共に歩み、育んでいきましょう」と呼びかけました。を守った人にお金が回る仕組みが必要です」と話しました。
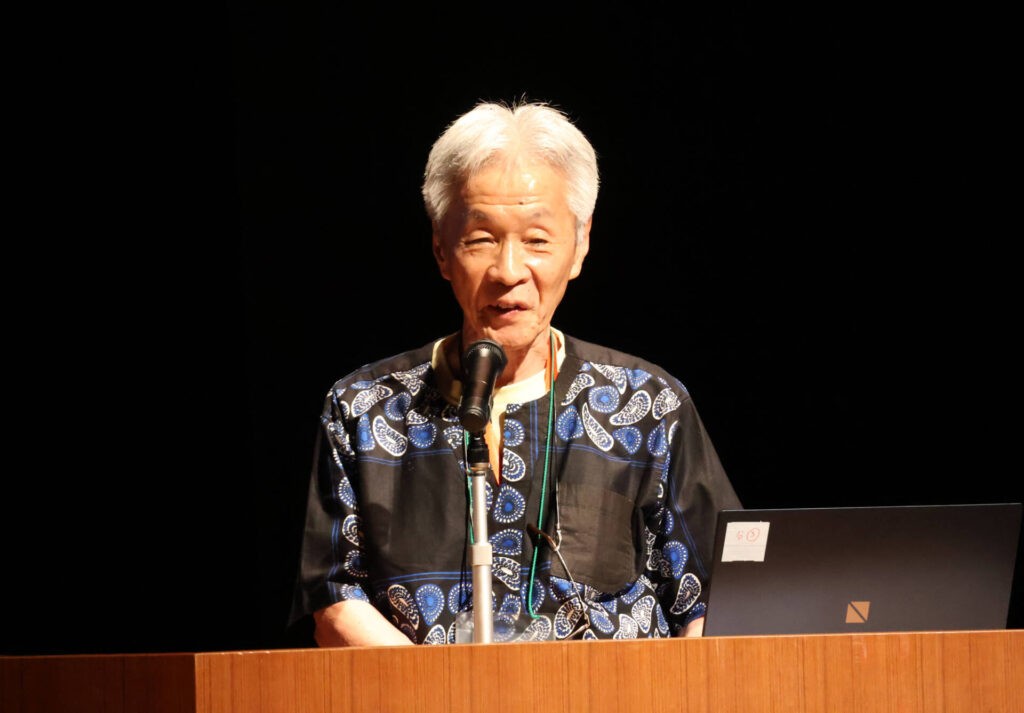
Table Vol.518(2025年10月)



