2025年3月5日、コープ自然派京都では、ネイチャーガイドとして日本各地で生物多様性について伝える坂田昌子さんの講演会を開催し、生きものの視点から食や農を考えました。
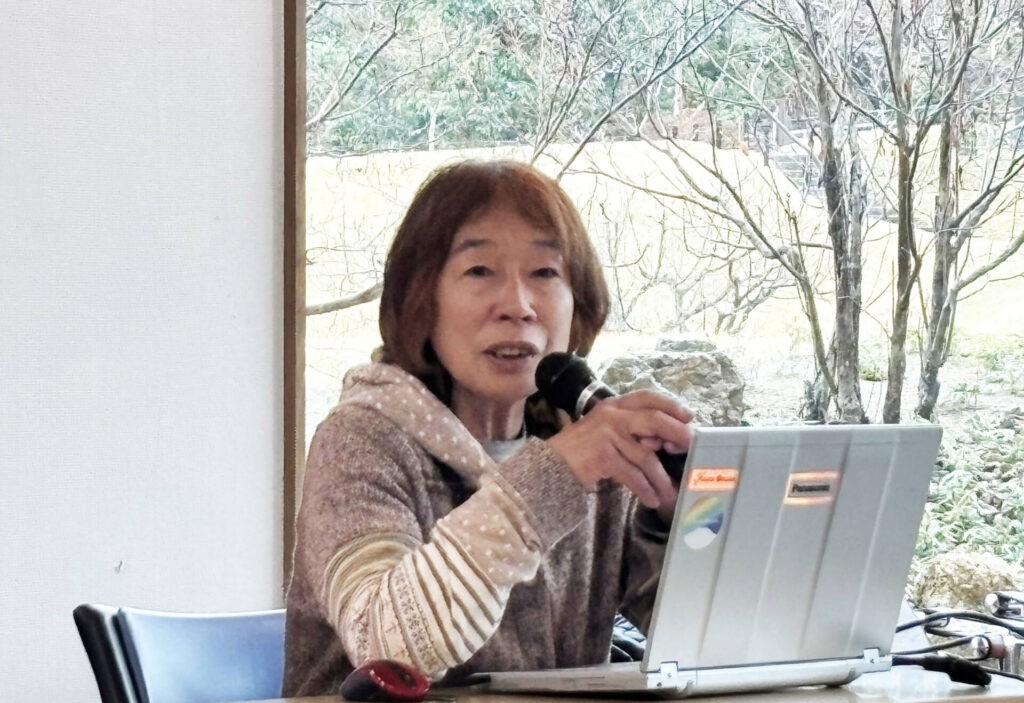
人間活動による大絶滅時代
2019年、地球の生物多様性の危機について「このまま放置すると、人間が把握している800万種のうち100万種が絶滅する」という報告が出ました(※)。日本では身近な存在のスズメ、ツバメ、ムクドリまでもが絶滅に向かっています。東京ではゲンゴロウ、横浜ではメダカが絶滅し、童謡などに当たり前に出てくる生きものが、すでに私たちの身近な環境から消えてしまいました。問題はそのスピード。過去1000万年の平均よりも数十倍~数百倍も速いといわれる現在の絶滅の主な要因は人間活動です。
(※)IPBES(生物多様性と生態系サービスに関する政府間科学政策プラットフォーム)による地球規模評価報告書
関係性まるごとを守る
けやきの木を1本切ると、その木を拠り所にしている昆虫や鳥、微生物、土壌菌などすべての命を奪うことになります。「2マイナス1=1にはならないんです」と坂田さん。兵庫県豊岡市で飼育コウノトリの野生復帰が成功したのは、コウノトリという一つの種だけではなく、エサとなるヘビやカエルを育む無農薬の田んぼや、巣を作るための松の大木に代わる巣塔を建てるなど〝コウノトリが生きる環境まるごと〟を復活させたからでした。
誰もが命の連鎖の網の目の中にいます。坂田さんは「自然との共存・共生とは、人の目線で仲良くすることだけではなく、食い食われるという命のやりとりを含めた関係になること」だと話します。
世界に例を見ない日本の里山
日本は、国土面積の4割が里山で、そこに昆虫、淡水魚類、両生類の7割が生息しています。里山の田んぼに水を溜めると、そこに両生類がやってきます。川とつながる田んぼは魚たちの産卵場所になり、とんぼ等の昆虫たちも産卵します。実に約6000種もの生きものが田んぼに生息しているのです。里山のような、人の手が入ることで生態系がより多様になっていく場所は世界にはほとんど例がないとのこと。その概念は「SATOYAMA」という言葉で世界に広がっています。

狩猟採集の意識を取り戻す
田んぼは米を収穫する場所であると同時に、おかずとなるドジョウ、ウナギ、フナ等を狩猟採集する場所でした。琵琶湖には今も「おかずとり」という言葉が残っています。材木も山菜も必要なときに山に採りに行っていたのです。「土地を大きく改変することも、採りつくすこともない狩猟採集の意識を少し取り戻すだけで、里山との適切な関わり方に近づけるのではないでしょうか」と話す坂田さんは、自然を畏れ敬う感覚が大切だと感じています。
食べるとは、自然を取り込むこと
食べるとは、自然を体のなかに取り込むことですが、この100年間で作物の品種は90%以上消え、体に取り込む自然の種類が激減しています。また、自然界から取り込む菌の種類が減ったことで、体内の菌の多様性も失いつつあり、アレルギー疾患や自己免疫疾患が増えています。さらに、自然と接する機会が減ったことが若年層の問題行動や疾患の原因の一つとして「自然欠乏症候群」の名で指摘され始めています。自然は〝嗜好品〟ではなく、人体にとって〝必需品〟なのです。
食の多様性から広がる世界
旬のものを食べることは、季節の移ろいを感じること。発酵食は冷蔵庫がない時代の保存法を知ること。そして、伝統食や行事食は地域の森川里海への敬意や感謝、そして祭りとも深く関わっていることに思いを馳せることができます。
「食の有機化が〝多様な生きものを育む〟という視点にたって行われたなら、私たちは食事を通して、命の逞しさと儚さを同時に知ることができるのではないでしょうか」。坂田さんは、食の時間をそんな物語に思いを馳せる時間にしてみませんかと呼びかけました。

Table Vol.515(2025年7月)



