2025年4月28日コープ自然派しこく(商品委員会)は、40年以上も前から有機の味噌・醤油をつくるヤマキ醸造(埼⽟県児⽟郡神川町)の逸見拓哉さんに、ものづくりのこだわりを聞きました。
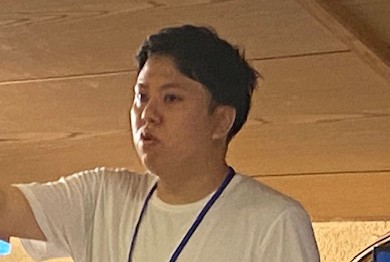
守る自然、残す自然
ヤマキ醸造では、オーガニックという言葉が一般的になる前から有機栽培の大豆を使ってきました。それは「買ってくれる人が健康でないと買い続けてもらえないし、土や自然にも負担をかけたくない」という想いから。高度成長期には「自然と人間の調和」を大切にするこの考え方を周りからからかわれたりもしましたが、こんな時代は永遠に続くものではないと信念を貫き、「守る自然、残す自然」を会社のコンセプトとしています。
水にこだわり工場を移転
1902(明治35)年に創業したヤマキ醸造は、埼玉県神川町で醬油をはじめとした大豆製品を中心に製造しています。当初は市街地に工場がありましたが、秩父山麓に囲まれた神川町の湧き水に惚れ込み移転。天然醸造の醤油づくりに欠かせない70個もの大きな木樽を一つずつトラックに載せて運び込みました。
土づくりから始まるものづくり
国産有機大豆は国内で年間に千トン流通していますが、ヤマキ醸造ではその4分の1にあたる250トンを使っています。「安全な食は原料を栽培する土づくりから始まる」と、耕作放棄地も活用した自社の有機の畑で大豆20トン、小麦30トンを育て、足りない分は長年契約している農家から購入します。農薬や化学肥料を使っていた畑を有機に変えるには3年かかるため、その転換期間につくった大豆も有機の価格で買い取り、特別栽培として販売し農家をサポートしています。
玄米糀へのこだわり
有機玄米の栄養価と旨みを活かした玄米糀もヤマキ醸造のこだわりです。一般的に白米糀が多いのは、玄米よりも糀菌が簡単につくから。まず、糀菌が玄米の中に入りやすくするために、表面にほんの少し傷を付けて精米します。そして、蒸した玄米に菌をつけて糀室に3日置き、機械を使わず外気で2~3日ほどかけてゆっくりと乾燥させます。

じっくりと時がつくる天然醸造
伝統的な天然醸造の醤油は機械による温度管理を行わないので、仕込みから出来上がるまでに1年から1年半かかります。その間は、職人が木桶ごとの個性を確認しながら、時をかけて発酵・熟成させて香りと旨みを醸します。熟成したもろみは濾布で包み、筒に入れて絞ります。搾る力が強いと大豆の雑味が出てしまうため、初めはもろみの重さだけで搾り、その後ゆっくりと油圧をかけて搾って醤油が出来上がります。

環境やフードロスにも配慮
東日本大震災の影響で計画停電になり、毎日の豆腐づくりに支障が出たことから、太陽光発電を導入してエネルギー面でも環境に配慮した取り組みを始めました。「とうふのマヨ」は、翌日の豆腐の注文数がわかる前に大豆を浸漬する必要があることから、多くつくりすぎた豆腐を有効利用するために商品化しました。他にも、豆腐づくりで出るおからはペットフードの原料として再利用し、醤油の搾りかすも牛のエサとして夏場の塩分補給に役立てています。また、森の保全活動にも力を入れています。
育てる人と食べる人をつなぐ
栽培から食べる人までの健康と伝統的な製法を守るヤマキ醸造。職人のなり手が少ないことや、洋食文化の拡がりで、特に若い世代の醤油の消費量が減少するなど課題はありますが、「今日のようにヤマキ醸造の醤油を使っているという声を聞くと鳥肌が立つほど嬉しいです」と逸見さん。これからも日本の文化である醤油のことやオーガニックの良さについて伝えていきたいとのことです。物価の高騰などによりひとり親家庭の生活状況は依然厳しく、継続したご支援は大変ありがたいです。モノとともに『どこかで誰かが見守ってくれている』という安心感をお届けできればと願っています」と話しました。

Table Vol.515(2025年7月)



