ICEBA(アイセバ/生物の多様性を育む農業国際会議)は、生物多様性を基盤とした地域循環型農業技術の確立と、国内外への普及を目指す国際会議です。2025年7月12日・13日には、7回目となるICEBA7が徳島県小松島市で開催されました。7月13日には、「中干ししない」米づくりを実践している地元の高校生の取組報告がありました。
徳島県立城西高校本校・神山分校では、中干ししない米づくりに挑戦しました。高校生を指導するのはJA東とくしまとNPO法人とくしま有機農業サポートセンター、田んぼ提供は地域の農家Orononoの松本直也さんです。
2024年11月 秋処理
JA東とくしまの西田聖さんの指導を受け、田んぼに残った稲わらを分解させるため、苦土(マグネシウム)、石灰(カルシウム)、鶏ふん堆肥を撒きます。これらの資材を使って土壌改良することで、田植え後のガス湧き(メタン・硫化水素)を防止するとともに、水や肥料をしっかりと保持し、水はけのよい土壌をつくります。

2025年5月 籾撒き
お湯で殺菌(温湯消毒)した種籾を、手作業で育苗箱に撒きます。1カ月ほどで苗が成長しました。

2025年6月11日 代かき
水を張った田んぼに、酵母菌と黒糖で作った酵母菌液を流し、有用な微生物の活性を促します。この時点で昨年の稲わらはもう確認できませんでした。トラクターで代かきをし、田んぼを平らに整えました。

2025年6月14日 田植え
いよいよ田植えです。地域のフリースクールの子どもたちや保護者も来てくれ、10人ほどで田植えをしました。田んぼに入るのも田植えをするのも初めての人ばかりでした。

中干しはいらない!
この後、この田んぼでは中干しは行いません。田んぼの土を乾かすことで有害ガスを抑制するとされますが、この田んぼにはガスの元となる未分解の稲わらがありません。
田んぼのガス湧き調査をしたところ、地球温暖化の原因のひとつであるメタンガスや、稲にとって有害な硫化水素ガスは全く検出されませんでした。また、中干しでは田んぼから水を抜いてしまうので、田んぼに生息する生物を脅かすことになります。中干しをしないことで希少な生物の命をつなぐことができます。
2025年7月の様子

これからの挑戦
参加した高校生たちは当初、中干しをしないで米が本当に作れるのか半信半疑でしたが、順調に育っている稲の様子を見て、「この技術がこれからの農業のスタンダードになっていきそうだ」と感じています。学校農場でも生物多様性を保全できる農法を試みているそうで、「改めて生物多様性の大切さを学んでいます」と話しました。
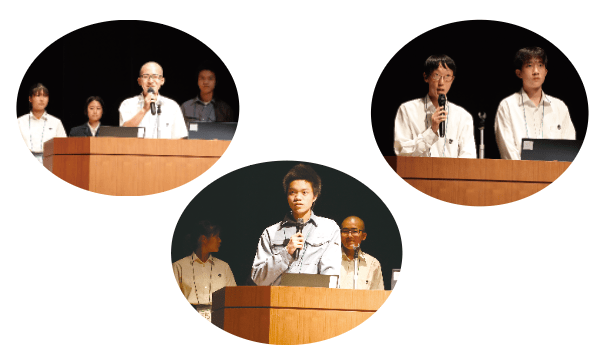
Table Vol.518(2025年10月)


