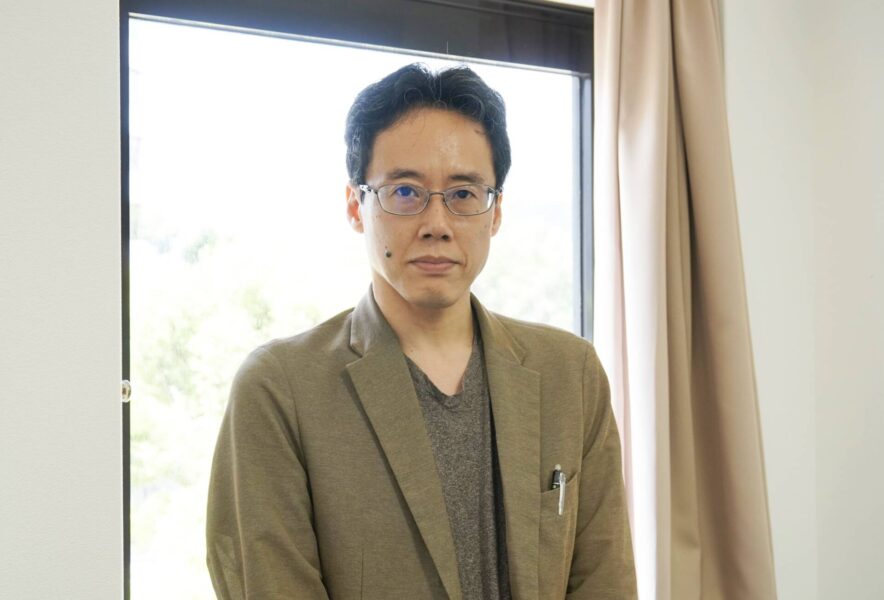政治は自分たちの声から遠く、戦争や分断のニュースばかりが目に入ります。戦争終結から80年という節目を迎える今、コープ自然派兵庫では総代会特別講演会として、政治学者の白井聡さんに現代の日本を生きる上での大切な視点を聞きました。
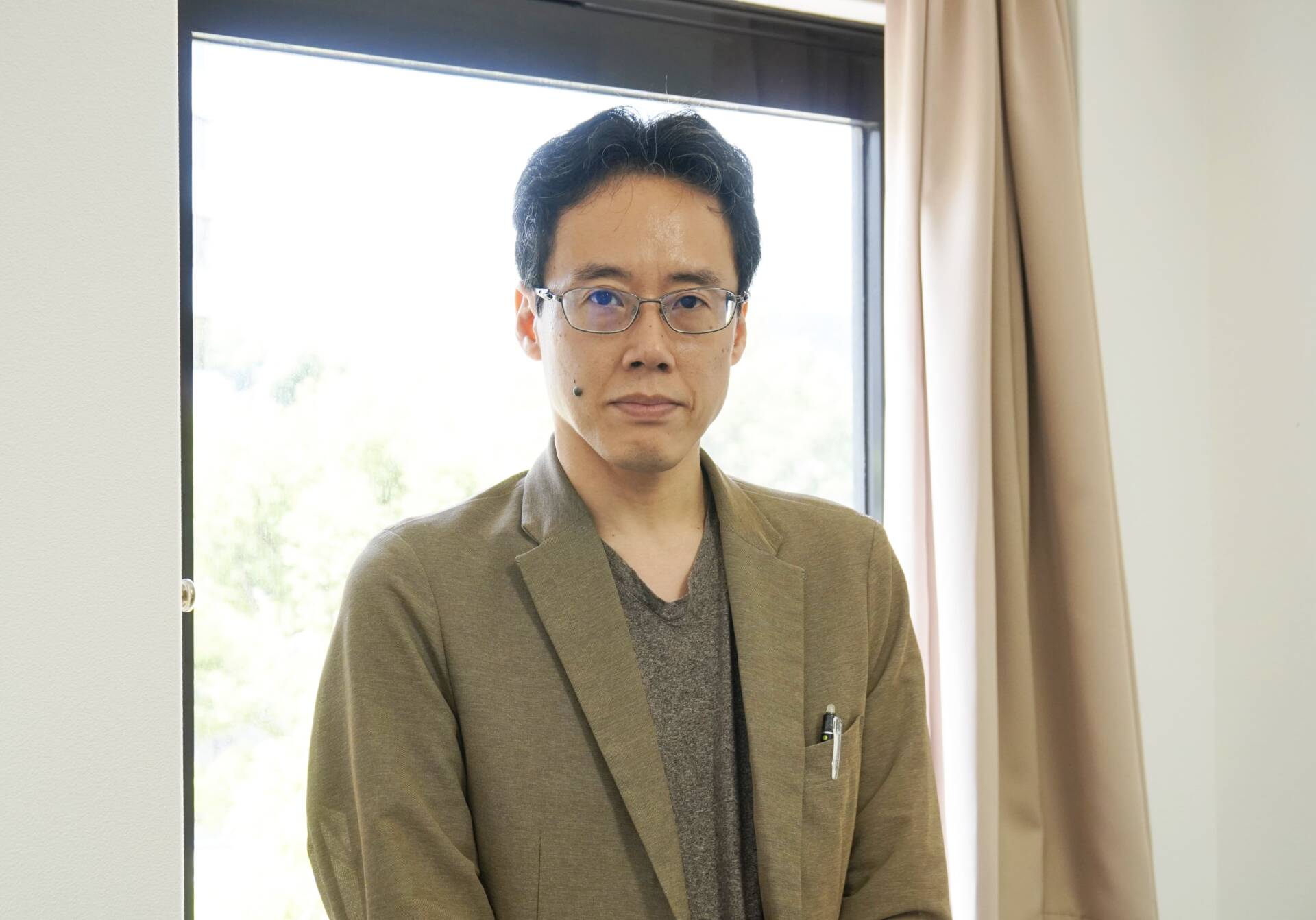
白井 聡| Shirai Satoshi
政治学、社会思想研究者。京都精華大学准教授。3.11を基点に日本現代史を論じた『永続敗戦論—戦後日本の核心』により、第4回いける本大賞、第35回石橋湛山賞、第12回角川財団学芸賞を受賞。著書に『国体論』『武器としての「資本論」』など。
分断と混乱の時代
イスラエル支援の欺瞞(ぎまん)
白井 世界中で分断や対立が激しくなっています。ロシア・ウクライナ戦争とイスラエル・パレスチナ紛争の着地点も一向に見えません。イスラエルとパレスチナの紛争では、G7※が共同声明でイスラエルの側に立つと宣言しました。歴史を振り返ると、イスラエルという国は、ヨーロッパにおける反ユダヤ主義・排外主義がナチスドイツにおいて極まり、もうこんな目に遭いたくないとユダヤ人が建国した国です。しかし、新しい国は誰もいない地域に作られたわけではないため、「パレスチナ問題」という形でずっと摩擦を繰り返してきました。その延長線上に今回のイランへの攻撃もあるわけですが、それを先進国がこぞって支持するというのは、自分たちがヨーロッパから追い出したユダヤ人たちが行っている暴力的行為を支持するという、いったい欧米の道義はどうなってしまったのかという状況です。日本は当初イスラエルを非難したのですが、結局はこの声明に賛成してしまいました。G7の姿勢は世界の分断をより深刻にする行為です。
※G7:アメリカ、イギリス、イタリア、カナダ、ドイツ、日本、フランス、及び欧州連合EU
無自覚な日本人
白井 歴史認識があってこそ、今が見えてきます。日本では「戦後」が語られますが、実際に総括すべきなのは「敗戦後」です。「敗戦」を否認してきたことが日本の政治と社会を歪め、劣化をもたらしてきた。海外では、日本がアメリカの属国だというのは共通認識です。アメリカに依存し、従属せざるを得ない国は他にもありますが、日本の特殊性は、日本人自身に従属している自覚がないことです。
最も分かりやすいのは沖縄の米軍基地問題でしょう。基地設置の根拠となる日米地位協定は、沖縄だけではなく日本全土に適用されています。しかし、米軍基地の75%は沖縄に集中しているため、沖縄の基地問題に関する報道は他人事として受け止められています。沖縄以外で米軍基地や日米地位協定の存在を自覚する機会は稀だからです。仮に、東京の六本木あたりに米軍ヘリが墜落すれば、日米地位協定が何なのか日本人全員が真剣に考えるようになるのかもしれません。この自覚の欠如が不健全な対米従属を永続化させています。
着々と進む台湾有事シフト
岸田政権の大軍拡
白井 日本にとっての懸念は、世界で起きている紛争が東アジアに飛び火してくることです。なかでも最大の懸念が台湾有事で、現に、それに対抗する準備として政府は防衛予算を増やし、敵基地攻撃能力(先制攻撃能力)を持つことを決めました。敵基地攻撃能力とは、ミサイル技術の変革により従来の専守防衛の考え方では間に合わないから、攻撃されそうな状況への反撃として敵基地を攻撃するというものです。しかし、実際的に考えて、「先制攻撃をしても専守防衛の範囲に含まれる」という理屈は成り立つのでしょうか。
専守防衛と敵基地攻撃の矛盾
白井 相手国が今まさに攻撃しようとしていて、実行寸前であることをどうやって立証するのでしょうか。また、そのような情報をどこから得て、それが信頼できる情報であることをどうやって証拠として提示できるのでしょうか。もし証拠を出せなければ、日本が一方的に攻撃したことにしかならず、国際法違反となります。攻撃対象として、相手国のミサイル発射基地や、滑走路などの軍事施設に加えて司令部や政府が想定されていますが、全面的紛争に突入するつもりなのでしょうか。そういったことを政府は具体的に考えているのか、極めて疑問です。
日米軍事指揮権の一体化
白井 日米の軍事指揮権の一体化が着々と進んでいます。有事になれば米軍と自衛隊は協調して一体的に軍事行動するといいますが、誰が指揮をするのでしょうか。国会答弁では「あくまで我が国の国益の観点から自主的な判断をする」と言っていますが、実際には、自衛隊はほぼ自動的に米軍の指揮下に置かれるでしょう。
日中戦争は空想的でしかない
白井 私は、台湾有事を契機とする日中戦争は本来起こりえないと考えています。なぜなら、日本と中国の経済的関係を考えれば、輸出・輸入ともに日本にとって最大の相手は中国で、食料品も肥料も中国から大量に輸入しています。もし戦争になれば日本経済は即座に崩壊し、餓死者までもが大量に出ることが想定され、戦争なんてできるわけがないのです。
しかし、安心はできません。日本はかつて「こんな戦争できるわけがない」という戦争を実際に行いました。太平洋戦争における対米戦です。絶対に負けると分かっていた状態で、合理的に考えればできるはずのないこと、起こるはずのないことが歴史的現実として起きたわけです。したがって、可能性は十分にあると考えて回避の道を探るべきだと思います。

特殊な対米従属の展開と現在地
戦争できる国へのターニングポイント
白井 2015年、安倍政権下で集団的自衛権の行使容認が行われたことは非常に大きなターニングポイントでした。これにより事実上解釈改憲したといってもいい出来事です。ところが他方で、集団的自衛権を認めることは、日米安保条約が軍事同盟であるとあらためて認めたことになるわけですが、日本には法律上「軍事」は存在しません。憲法第9条第2項に軍事を持たないと明記する国が軍事同盟を結ぶとはどういうことでしょうか。狐につままれたような気持ちになります。
安倍政権は「積極的平和主義」を打ち出しました。消極的平和主義よりも積極的な平和主義の方がよさそうに聞こえますが、これまでの戦争からできるだけ身を遠ざける消極的な安全保障政策から、積極的に敵を攻撃する方向に転換するということです。要するにこれは、アメリカの軍事戦略をより積極的に支えていくということであり、対米従属を深化させることにほかなりません。
憲法より上位にある日米安保条約
白井 実質的な日本の最高法規は日米安保条約であり、その下に日米地位協定があり、日本国憲法はその下の位置付けです。こんなにおかしなことになっているのは、戦後の民主化が極めて不徹底なものに終わってしまったからだといえます。戦後、アメリカは日本の民主化と非軍事化を推し進めますが、共産主義勢力の拡大を恐れて早々に方向転換しました。そして、戦争責任追及が不徹底なままA級戦犯被疑者が政財界のトップに立ち、日米安保体制を確立し、経済復興を進め、敗戦の影響を速やかに忘却して親米保守が愛国者を自称する戦後日本の形がつくられたのです。
「戦後の国体」の起源
白井 不健全な対米従属の特殊性は、戦前の天皇制に由来するというのが私の仮説です。大日本帝国における天皇制は、「天皇陛下の赤子(せきし)」という言葉があるように、天皇は国民を我が子のように愛し、国民はその愛に応えるという世界観に支えられていました。応えるというのは、いざ有事の際には「天皇陛下のために死ぬ」ということです。戦後、この天皇の位置をアメリカが占めている。戦後の日本の政治史を理解するためには、そのように見定めるのが必要ではないかと考えました。
アメリカは日本を支配し従わせているのではなく、日本を愛してくれているという妄想の中で日本人は生きています。本来、国と国との関係はビジネスライクなものであり、アメリカは自国の国益のみを考えて行動しています。1951年、日米安保条約交渉に先立ち、ダレス国防長官は「日本に、われわれが望むだけの軍隊を、望む場所に、望む期間だけ駐留させる権利を確保できるか、これが根本問題だ」と発言していました。アメリカが慈悲深い存在のように見えたとすれば、かつて東西対立のなかで、アメリカが日本をアジアにおける最重要パートナーとして様々な面で優遇していたからでしょう。しかし、東西対立が終わり、ソ連が崩壊・消滅してすでに35年。アメリカにとって日本が援助すべき同盟者ではなく収奪の対象となったいま、「それでも日本人はアメリカのために死ねるか」という究極の問いを私たちは突きつけられているのではないでしょうか。
アメリカの衰退
《帝国》の店じまい
白井 しかしいま、対米従属は強制終了されようとしています。なぜなら、アメリカが衰退してきたからです。アメリカは2000年代以降、対テロ戦争やリーマンショックなどを経て国内の経済格差が拡大し、深刻な荒廃が広がりつつあります。見捨てられたと感じた人々のリベラル・エリートへの嫌悪感は、トランプ大統領再選につながりました。トランプ大統領がやろうとしていることは、軍事負担の放棄や関税政策による国内製造業の復活などですが、指向しているのはひとことでいえば「帝国の店じまい」です。しかし、うまくいくかどうかは未知数です。
グローバルサウスの台頭
白井 アジア、中南米、アフリカなどグローバルサウスの台頭が顕著です。ウクライナとロシアの紛争が始まったとき、アメリカを始めとする先進国はロシアを非難し、経済制裁を加えました。ところが、その制裁に加わった国は、実は少数にとどまっています。制裁に加わったのは、ヨーロッパ諸国、北米のアメリカ、カナダ、オセアニアの中心国であるオーストラリア、ニュージーランド、アジアでは日本、韓国、シンガポール、台湾だけです。ラテンアメリカやアフリカで制裁に加わっている国はありません。
これは、先進国とグローバルサウスの国力の差が縮まってきたことの現れです。先進国はこれまで経済的優位性を盾に自分たちの意思を押しつけてきたわけですが、その力が弱くなっています。グローバルサウスの国々にとっては、ロシアの行為を帝国主義的なものとして批判するアメリカなども、同じように帝国主義を振りかざしてきた存在です。「お前たちにそんなことを言う資格はないだろう」というわけです。
自立の覚悟が必要
白井 日米安保条約に合理的な必然性はすでにありません。アメリカの国力も衰退するなかで日本の自立は不可避です。問題は、その覚悟が日本の国民にあるかどうかです。戦後、日本の平和はアメリカの掌の上に限定された民主主義と、アジアでの戦争を利用した繁栄に支えられた物語にすぎませんでした。対米従属は目的ではなく手段であったことを思い出し、棚上げしてきた諸問題に向き合うことが求められています。世界の情勢を冷静に見極めながら、自立の道を探っていかなければならないときです。
Table Vol.516(2025年8月)