コープ自然派事業連合は大阪府南部で福祉事業を行うオレンジコープとの組織合同により、ともに新しい福祉モデルを拡げていくことになりました(詳しくはこちら▶)。オレンジコープの取り組みを牽引してきた笠原優さんに、生協の「尊厳を大切にする」福祉のあり方について聞きました。

ここではピザ窯のあるイタリアンレストランや乗馬クラブ、農園、花壇などで障碍者が働いています。
笠原 優 | Kasahara Masaru
生活協同組合連合会コープ自然派・オレンジコープ事業連合(厚労省認可申請中) 副理事長、オレンジコープ(泉南生活協同組合) 理事長、社会福祉法人野のはな 理事、社会福祉法人聖和協働福祉会 理事
オレンジコープの福祉
オレンジコープのはじまり
笠原 オレンジコープの歴史は、1950年に大阪の泉南郡岬町に前身となる緑ヶ丘生協が設立されたことにさかのぼります。戦時中、岬町では川崎重工が小型の潜水艦をつくっていました。戦争に負けて工場の閉鎖が決まり、会社の共同浴場がなくなると地域の人たちの風呂がなくなってしまうということで、みんなで資金を出し合って、風呂を買い取るためにつくったのが緑ヶ丘生協でした。業務のスタートは風呂屋だという生協です。その後、家庭風呂の普及などで経営が悪化し、立て直すために共同購入が始まりました。
組合員の老後を支える
笠原 1990年代の終わり頃、当初から生協を支えてきた組合員は年齢を重ね「生協で私たちの行く末をなんとかしてほしい」という声が高まっていきます。介護保険事業を検討し始めたのは介護保険法ができる前のことで、2000年に法律施行と同時に事業を開始しました。
介護保険法は、事業所から住まいを訪ねてケアすることが前提の制度です。しかし、私たちは介護と住まいをセットにして、組合員が高齢になっても最期まで安心して暮らせるものをつくりたいと考えました。組合員のニーズを考えると、おのずと住まいづくりが事業の中心となっていったのです。
「終のすみか」を
笠原 高齢者住宅を始めるときに私たちが決めたのは、制限をかけないということ。自分の家に住んでいるのと同じでいいですよ、と。鍵もかけません。一般的な高齢者住宅では、玄関には鍵がかけられて出入りが制限され、エレベーターのボタンを押せないところもあります。つまり、いったん入ると出られないようになっているんです。お酒やタバコも禁止、家族や友人の訪問も制限されます。ペットは飼えず、消灯時間が決まっているところもあります。でも、大事にすべきなのは、その人自身が何を望んでいるのか。その人らしく普通に暮らせるということが基本であり、尊厳を大切にすることが私たちの理念です。
「尊厳を守る」ということ
笠原 尊厳を守るとはどういうことか、具体的に話をしましょう。オレンジコープが最初に建てた有料老人ホームに、認知症が進んで一人では生活ができない、けれど自由に暮らしたいという方がおられました。その人のいちばんの願いは、死ぬまでタバコを吸いたいということでした。でも、認知症が進むにつれて火の不始末は増えていきます。スタッフは本当にこのままでいいのかと悩んで相談にやってきました。そのときに私が言ったのは、「火事で死ぬリスクがあることも分かった上でその人はタバコを吸いたいのだから、かまわない」ということでした。
その人からタバコを奪うのはすごく簡単なんです。逆に、自分の部屋で好きな時にタバコを吸えるように支援するのはものすごくリスクがあって難しいことです。責任者の覚悟が問われます。お酒も、飲まない方がもめ事は起きにくい。でも、自分の家であれば当然、なにをするかは自分で決められるわけです。その人は結局、最期までそのホームに住んで、亡くなりました。家族からは「本当に自分らしい生き方ができました」と感謝されたことを今でも覚えています。
外に出る自由
笠原 別の認知症の方は、夜中に外に歩きに出た時に、電車にはねられ亡くなってしまいました。スタッフが一緒について出て見守りをしていたのですが、途中ではぐれてしまい、探している間に電車にはねられてしまいました。警察や行政からは管理体制を問われましたが、それでも私たちは、鍵を締めて出られないようにすることが正解だとは思えませんでした。鍵をかけることは簡単なんです。でも、それではその人が自由に外に行きたいという意思を尊重できません。こういうときこそ、制度より理念を徹底できているかが問われる瞬間です。
自由を守るリスクマネジメント
笠原 もちろん、リスクマネジメントはします。自由とほったらかしは違いますから。人命や利用者の安全を最優先に、もし異常が起きた時にも安全な状態を維持できるように考えます。例えば、徘徊のリスクのある人が部屋のドアマットを踏むと事務室のブザーが鳴って、スタッフが付き添いに行きます。手厚い見守りをするには余分に人の配置が必要なので、すごく費用がかかります。それでも制限を加えることはしない。外に出てしまう人には、夜中でも手をつないで一緒に出かけます。物理的な対策と見守りで取り除けるリスクは取り除き、その上でどうしても残るリスクには、自由度を下げない方法で対策を考えます。
また、本人や家族とのコミュニケーションがとても大切です。私たちは契約する時に、本人と家族に「自由ですけれど、自己責任ですよ」と話します。想定できることはすべて伝えた上で、判断するのは本人と家族です。そして、入居後は家族への情報提供を欠かしません。速やかな情報提供と丁寧なコミュニケーションこそが、最大のリスクマネジメントだと思っています。
自分の親に住んでもらいたい場所
笠原 こういうやり方を続けるためには、スタッフがしっかりと理念を理解していることが重要です。働くスタッフには、「自分の親に住んでもらいたいと思える場所になっているか」を問います。自分の親に、監視カメラに見張られ、閉じ込めるような生活を送らせたいのかということなんです。現場では日々いろいろなことが起きます。だからこそ、揺るがないように何度でも理念に立ち戻ることが必要だと思っています。
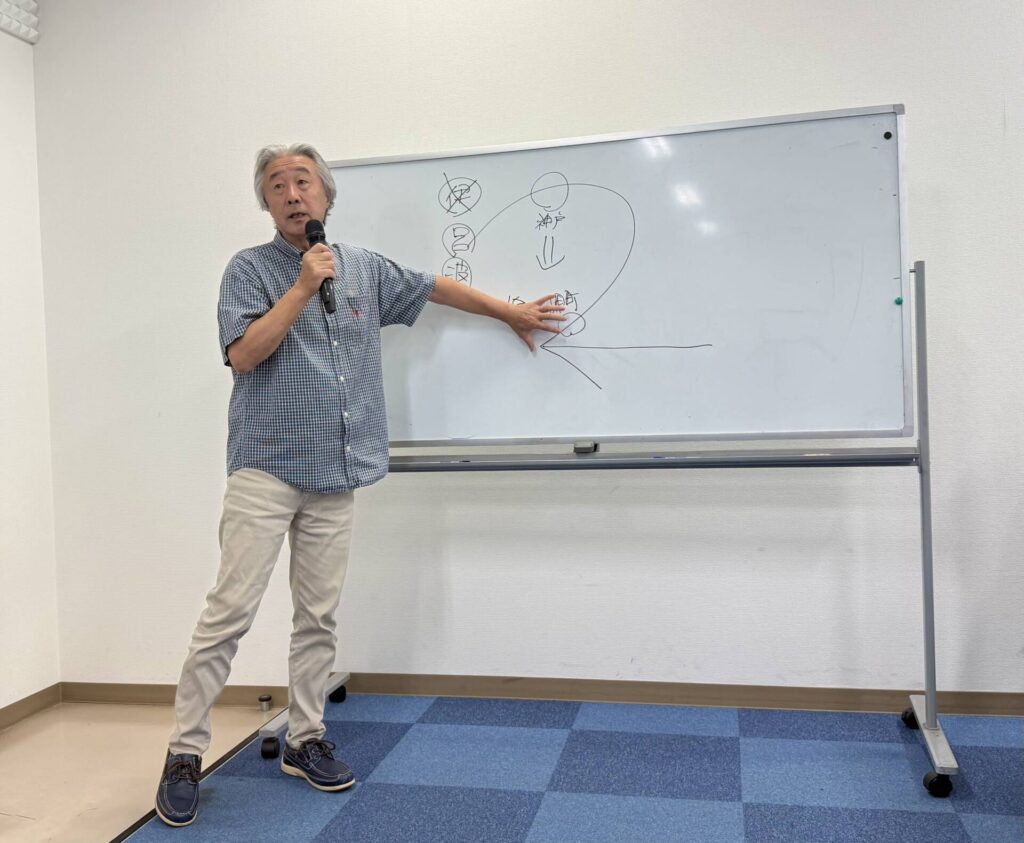
めざす障碍者支援のかたち
障碍者の就労支援
笠原 オレンジコープでは、2003年に「社会福祉法人野のはな」を設立し、高齢者の住まい事業と、障碍者の就労支援事業をセットで行なってきました。現在、オレンジコープの介護付き住宅、分譲マンション、サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)などで約1000人の高齢者が暮らしていて、いつも満室です。
高齢者住宅で提供する食事はすべて障碍者の就労支援事業でつくっています。農場、野菜カット工場、セントラルキッチン、レストラン、パン屋、乗馬クラブなどを持ち、すべての場所で障碍者が働いています。また、乗馬クラブの馬ふんで堆肥をつくって農場で活用するといった循環型の農福連携にも取り組んでいます。
障碍者が自分自身で生きる
笠原 さらに、障碍者が介護福祉士の資格を取るチャレンジを始めています。高齢者の安否確認や生活支援を障碍者が訓練として行うことで実務経験を積んで、介護福祉士の資格取得につなげます。これまで、障碍者年金と工賃(賃金)でグループホームでの自立生活を実現するモデルを進めてきました。これをさらに発展させて、介護福祉士としての就労をめざしています。
地域に溶け込む
笠原 障碍者の自立には地域の理解が不可欠です。グループホームを地域につくるとき、なかには障碍者が来ることを漠然と怖いと思っている人がまだまだいます。事前に住民説明会などを開くのですが、実際に住んで生活をし始めると、歩いているだけで「怖い」「子どもに何かされるのではないか」という声が出るのが現実です。
そこで私たちは、障碍者のことを知ってもらうことから始めました。地域の清掃活動やイベントに積極的に参加して作業をするなかで、説明会を何回しても伝わらないことを感じ取ってもらえます。そして、ほかの住民を説得する発信者にもなってくれます。発信者が増えることは、福祉に関してとても大切なことだと思っています。
もうひとつ、グループホームの表札に「グループホーム〇〇」ではなく、住む人たちの表札を出しているのも大きな特徴です。施設を運営しているのではなく、そこに住む個人を尊重しているということです。そして、障碍者自身にとっても地域に自分を位置づける役目を果たしているように感じます。
ともに生きるコミュニティを
目の前の人をまっすぐに見る
笠原 福祉というと、専門家やプロなど、自分ではない誰かがやっているイメージを持つ人も多いと思います。でも、福祉というのは、素人の目線でいいと思うことを素直にやることが一番なんです。制度や誰かがつくった“正解”に当てはめようとするのではなく、目の前の人をまっすぐに見ること。福祉は、高齢者や障碍者だけではなく、生まれる前から死ぬまで全員が関わるものです。だからこそ、難しく考えるのではなく、どういうものなら一番楽しく自分らしく暮らせるかを、全員で考えることが大切です。
サ高住を中心としたケアのコミュニティをつくる
笠原 コープ自然派・オレンジコープ事業連合として、自分が住みたい場所、関わりたい福祉を「コミュニティ」としてつくっていけたらいいですね。また、コープ自然派が力を入れてきた国産オーガニックの実績を福祉事業でも展開できたら、社会への大きな訴えになると思います。
年齢も性別も、障碍の有無やルーツなど、いろんな人たちがみんな「自分の居場所」だと感じられるようなコミュニティが必要だと思っています。障碍者は人口の10%、約1200万人いて増加傾向です。貧困の人たちも、外国人労働者も増えています。こうした人たちへのケアや支援も必要になっていくなかで、サ高住を中心にコミュニティをつくれば対応ができるんです。みんなが集まりやすいレストランやカフェ、障碍者のグループホーム、保育園、畑や田んぼなど、それぞれの地域でやりたいこと、必要なことを高齢者福祉と障碍者支援をセットで組み立てていくとおもしろいことができるのではないでしょうか。
その時々の生活者が切実に望むことを実現するのが生協の役目です。だれの尊厳も排除しないで、みんなが「その人らしく」安心して暮らせる地域社会をつくる。このような考えに共感する人にたくさん集ってもらって、一緒に夢を叶えていきましょう。
Table Vol.519(2025年11月)


