気候変動と海洋の環境変化が水産資源に大きな影響をもたらしています。連合商品委員会では2025年2月21日、一般財団法人漁港漁場漁村総合研究所の伊藤靖さんを招いて水産資源の変化を学び、各地の生産者に海の現状や取り組みを聞きました。

先細りする日本の漁業生産と消費
日本の漁業は80年代が生産量のピークで、この頃の日本は世界最大の漁業国として知られていました。その後、漁獲量は徐々に減少し、現在はピーク時の3分の1に。日本人の魚介類消費量は1990年の約半分以下になっています。
海面水温の上昇で水産資源が減少
地球温暖化で世界的に海面水温が上昇する中で、特に日本近海は世界平均の約2倍の上昇率です。「海洋熱波」と呼ばれる水温が過去数十年に比べ高い状態が続く現象はこの100年で大幅に増加。海面近くで産卵するイカや、海面近くで生育するサンマなどに変化を及ぼしています。海外の事例では、海の中底層域のマダラやズワイガニもエサ不足により減少しています。
魚種の変化に合わせた対応を
海水の温度変化は、魚の分布や漁獲量に影響を与えます。東北の太平洋側では暖かい海域に棲む魚が増え、これまで東北で獲れていたマダラは北海道で漁獲量が増えています。北海道や東北ではサンマやサケなど特産の魚が不漁になり、ブリやヤリイカが増加。行政からの支援を受け、ブリが棲みやすい水深の漁場へ変更し、ヤリイカの産卵に適した水温の深さに産卵礁を整備するなど、新しい魚種に合わせる取り組みを行なっています。 また、漁獲量減少により少なくなった加工場の数では処理が間に合わないため、急速冷凍や流通技術で鮮度を保ち、地元では価値のない魚を珍重される地域へと流通させる工夫もしています。
近年の急激な魚種の変化には人側の対応力が必要です。伊藤さんは、「昔はマグロのトロは人気がなく捨てていたように、廃棄している未利用魚を食用にしたり、定番の魚しか売らないスーパーではなく、多様な魚の食べ方を伝えながら販売する店を増やすことが必要です」と話しました。
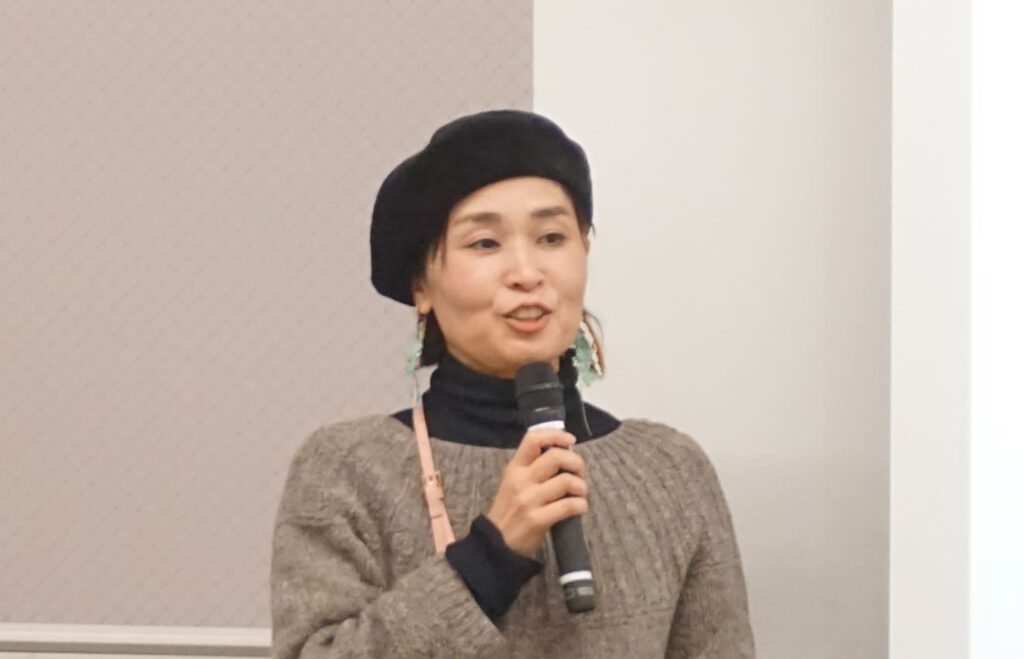
産地からの報告
鳥羽磯部漁協の小野里さんは、「黒潮の蛇行により三重県志摩近辺の海は温暖化が進み、アラメなど魚の棲み処になる藻場が磯焼けで減っています」と話します。漁協では、藻場を食べてしまうアイゴを氷詰めで鮮度を保ち、食用に加工する様子を報道してもらうなど、海の現状を伝える活動をしています。

香川県の水産加工メーカー・キョーワの加地さんは伊吹島名産の伊吹いりこについて、「海水温上昇などの影響で脂が乗りすぎ、干物にすると酸化するので、イワシが瘦せる頃を選んで漁をしています」と話します。また、「伊吹島プロジェクト」として、脂の乗ったイワシを釜揚げにして急速冷凍する新しい食べ方を提案。「主要な産業である漁業を活性化させて島を存続させたい」と語りました。
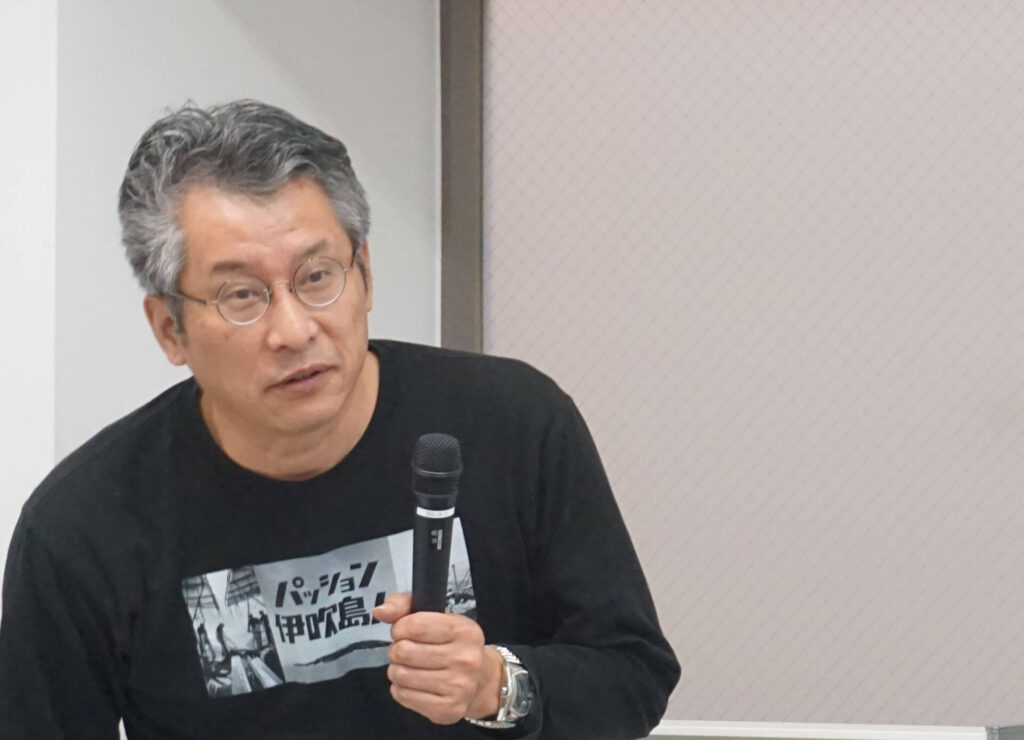
鳴門魚類の山本さんは「自然派Style雄武秋鮭を水揚げする北海道の雄武漁協では、資源保護型漁業により秋鮭漁を管理し、『10年後は10年前から』の考えから植樹活動や漁場の整備、稚魚の放流をしています」と話します。しかし、南半球の海水温上昇で生態系が変化し、放流した秋鮭が雄武漁協へ戻らない可能性もあります。「温暖化の研究の進化を待ち、コープ自然派と一緒にできることを考えたい」と語りました。

わたしたちができること
魚料理が苦手な組合員も利用したくなる商品づくりや、産地に寄り添うことが日本の水産の未来につながります。連合商品委員長の正橋さんは、「組合員と生産者、職員みんなで海の状況変化について考えることが大切です。定期的に魚を食べ、持続可能な水産をめざしましょう」と訴えました。

Table Vol.514(2025年6月)


