水俣病が公式に確認されてから67年。その教訓を語り継ごうと、2023年4月29日、京都で記念講演会が開催されました。

水俣病の記憶を紡ぐ
水俣病は、熊本県水俣市周辺で、チッソという会社によって引き起こされた公害病です。1950年代から1960年代にかけて、チッソ水俣工場からメチル水銀を含む有毒物が大量に不知火海に排出されました。それが魚介類の体内に蓄積され、魚を食べた人に重い神経症状を引き起こしました。患者認定や損害賠償の裁判は現在も続いており、いまなお問題は終わっていません。
水俣病は日本が強引に近代化を進める中で、経済成長の代償として引き起こされました。今回登壇した4人の講演に共通していたのは、この現代日本の在り方を問うとともに、水俣病の悲惨さや闘争の歴史だけではなく、そこには多様な人間がいて、様々な感情や葛藤があったことをまるごと伝えていきたいという思いでした。
道子と京二の闘争
元毎日新聞記者で作家の米本浩二さんは、水俣病闘争を言葉によって支えた『苦海浄土』の著者である石牟礼道子さんと、その執筆活動を支えた渡辺京二さんの関係性に着目しました。水俣病闘争の歴史には数々の印象深い言葉がありますが、闘争を広く伝える言葉の多くは石牟礼道子さんによって生み出され、渡辺京二さんによってかみ砕いて伝えられました。二人は互いに特別な結びつきを感じており、その熱が闘争の熱となっていたといいます。空疎な言葉ではなく、体とつながる言葉が世の中を動かしていったひとつの証左がここにありました。

悲惨さについて
社会学者の立岩真也さんは、学者として、アーカイブ(記録)を残すことに熱心に取り組んでいます。きっとそこからの実感なのでしょう、何度も「水俣病はまだいい」と発言しました。多くの人が関心を持ち、行動し、言葉が積みあがった水俣病は、忘れ去られて闘争の歴史が残っていないほかの問題、例えば薬害スモン事件などと比べるとまだいいと。そして語り方について、こんなに悲しいことがあった、糾弾すべきことがあったというその悲惨さはもちろん語るべきだし、聞くべきだけれども、悲惨というだけではない複雑性もきちんと表現してきたのが水俣の特筆すべきことではないかと話しました。
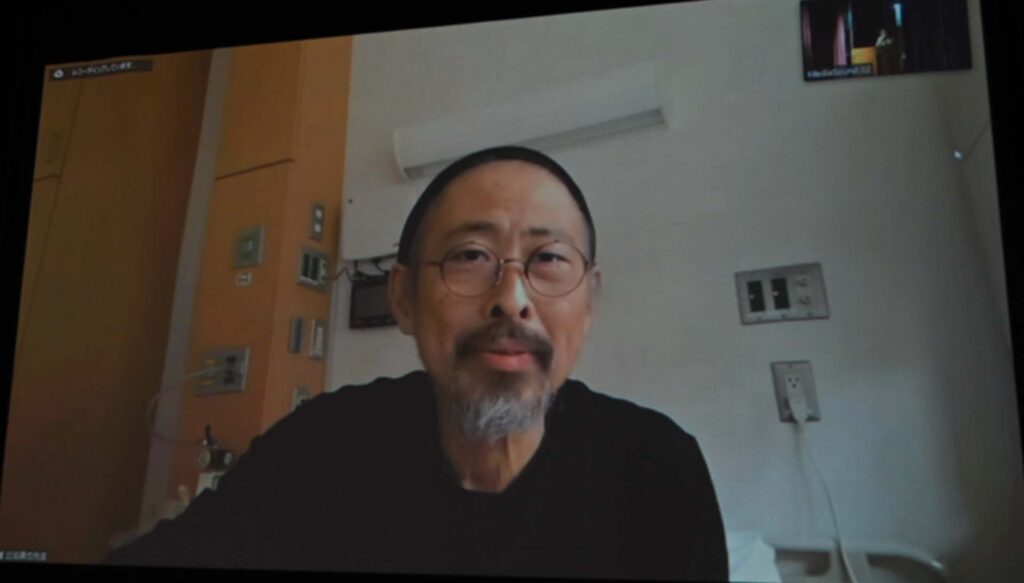
世界はもっと豊かだし、人はもっと優しい
映像作家の森達也さんの話は、はるか昔の話から始まります。450万年前、アフリカに登場したラミダス猿人は、地上にはじめて下りた我々の祖先でした。しかしヒトは極めて弱い生き物です。木の上ならまだしも、地上には敵がたくさん。だから群れで生きることを選択しました。群れることで、言葉や文字が生まれ、社会性を獲得していきました。
不安や恐怖を持ったとき、人は言葉(指示)を求めます。この20年、集団化の傾向が一層強まっているように感じます。プーチンや金正恩の名前を挙げるまでもなく、独裁的政治家が台頭してきたのは指示、つまり強いリーダーシップを私たちが求めたからです。集団化とは、分断化とイコールです。集団であるための同質の何かを持っていない人を排除、分断して、集団の中では個が消えていきます。主語が「私」ではなく「私たち」になり、同じ方向に同じスピードで動く人たちの中で周りに合わせているうちに、方向が変わってもスピードが出過ぎても気づかず、暴走して大きな過ちを犯してしまう。歴史はその繰り返しです。森さんの原点は1995年のオウム真理教のドキュメンタリー映画です。このとき、信者はみんな善良であること、集団はその善良な人たちの行動を変えることを知りました。その究極が軍隊です。日本人は特に個が弱く、組織になじみやすい性質があります。戦前は天皇をシンボルとする国体に、戦後は企業に滅私奉公してきました。そして、日本人のもうひとつの特徴は忘れっぽいということです。12年前、あれだけ大きな原発事故を経験しながら、もう原発新設や運転期間延長を決めている。水俣病は、そんなこの国の忘れやすさからするとありえないくらい忘れられていない事件ともいえるでしょう。
モンゴルに行ったとき、羊の群れを見ました。よく見るとどの群れにも、羊100頭につき1頭の割合でヤギがいます。なぜヤギを一緒に飼うのか不思議でしたが、羊は家畜化の過程で個を失ってしまい、雨が降っても食べる草がなくなっても、その場でぼーっと立っています。ヤギは雨が降ったら雨宿りできるところへ移動し、食べる草がなくなったら草のある場所に移動する。そのヤギに付いて羊は移動するのだそうです。日本人は羊度が高いと言えます。もう少しヤギ度を高めた方がいいのではないでしょうか。

棄てられて
水俣病患者の小笹恵さんは、水俣病関西訴訟の原告団長として活躍した岩本夏義さんの娘さんです。小笹さんは長い間、父親のことがイヤでイヤで、水俣のことを隠して隠して生きてきました。大阪に引っ越さざるをえなかったのも、家が貧しいのも、すべて父親のせいだと思い反抗して生きてきました。でも父親が、裁判で負けた患者さんやお世話になった医者や看護師、みんなに謝りながら亡くなっていったのを見たとき、「なんで父が謝らないといけないのか」「父には誰が謝ってくれるのか」という思いがあふれ、国や県の役人を仏壇の前にひざまずかせたいという思いで原告団の会議に行くようになりました。また、語り継げる者は自分しかいないのではないかという思いから、講演をするようにもなりました。亡くなって30年経っても皆に名前を憶えられている父が、今はいちばん尊敬している人です。
被害者遺族として闘ってきた小笹さんですが、自分自身が水俣病の検査をすることには強い抵抗感がありました。長年、検査をする人はお金目当てという偏見を、自分もどこか持ってしまっていたため、父の入院や他の患者さんのつきそいで毎日のように病院に行っていても、そこで自分が検査をするということは思いもしませんでした。関西在住の小笹さんが熊本まで検査に出向き、ようやく患者認定申請をしたのは2005年のことでした。

語り継いでいくために
水俣病闘争の中にも、恋があり、嫉妬や羨望があり、親子の反発がありました。水俣の中にもともとあった差別、水俣病に対する差別、認定されたか、訴訟を起こすかどうかで細かく分断されていく被害者、親類縁者の誰かはチッソで働いているという関係性、誰かのためには闘えても自分自身を患者だと認めることの困難さ……。漁師の緒方正人さんは「チッソは私だった」と言いました。魚からみると自分はどうみえるだろう。自分がチッソ社員だったら何をしていただろうか。悪とは何か、善とは何か。
以前、コープ自然派おおさかの理事研修で水俣を訪れた参加者の「水俣といえば水俣病のイメージしかなかったけど、そこは水俣市というふつうの街で、そこに暮らす人たちの生活があるんだということが、実際に行ってみてよく分かった」という言葉が思い出されます。当たり前のくらし、ごくふつうの日々の大切なくらしを守りたいという、ただそれだけのための闘争が、いかに難しいか。水俣、福島、広島、長崎……その地で何が起きたのかを知ることはとても大切です。でも、そのときに、その土地も、そこに生きる人も多様であり、複雑で繊細なまるごとを知る努力をしなければと思います。

Table Vol.491(2023年7月)より
一部修正


