ICEBA(アイセバ/生物の多様性を育む農業国際会議)は、生物多様性を基盤とした地域循環型農業技術の確立と、国内外への普及を目指す国際会議です。2025年7月12日・13日には、7回目となるICEBA7が徳島県小松島市で開催されました。
7月13日、分科会1では、田んぼの生きもの調査活動を通して連携が広がった韓国や台湾からもゲストを迎え、各地の取り組みが共有されました。

~韓国~
韓国の生きもの調査と生態環境
韓国では2006年に行われた「日韓合同田んぼの生きもの調査」をきっかけに調査が始まりました。泥の中のミミズを調べるなど日本の調査方法が韓国各地に広がり、「田んぼも湿地だ」という認識につながっています。
ポンハ村では都市開発が進む中、環境にやさしい農業を続けることでコウノトリが田んぼに飛来し、野生復帰に貢献しています。また、子ども向けの体験学習として、生きもの調査のほか田植えや稲刈りなども行っています。「健全な食べものを提供してくれる田んぼはその水で気温を下げ、生物多様性を育んでくれる私たちの宝物です」と林さんは話しました。田んぼの生きもの調査を基本として、日韓が刺激をしあいながら田んぼの体験と湿地教育が進められています。

~台湾~
台南市の環境にやさしい農業の推進
台南市官田地区は、台湾新幹線の建設で生息地を追われた希少な水鳥レンカクの保護区で、台湾で人気食材ヒシの実の主産地です。レンカクはヒシなどの浮葉植物に巣を作りますが、ヒシは植え付けから収穫まで手作業で行うため、人手不足で栽培面積が減少。また、農薬散布によってレンカクなど多くの水鳥を失ないました。そこで、エコ農業とレンカクの保護に協力する農家は、林業自然保護省が発行する「グリーン野生生物保護ラベル」を取得することでより有利な価格で販売できる仕組みを作り、農家と協力関係を築いて課題に取り組んでいます。
舩橋さんから、環境教育を通して地域の人たちが有機的につながり一緒に新しいことを考えていく風土、意識が変わっていくことの大切さが語られました。

~日本(宮城県大崎市)~
絶滅危惧魚の最後の砦、里山ため池を守る
1993年、宮城県大崎市の里山ため池で60年ぶりに絶滅危惧種の淡水魚シナイモツゴとゼニタナゴが見つかりました。この地域は江戸時代に始まった干拓により水田が広がり、生物多様性を保つ伝統的な水管理システムは2017年「世界農業遺産」に認定されました。しかしオオクチバスの侵入で在来魚は絶滅の危機に。そこで、ため池の池干しを行ってオオクチバスを完全駆除し、豊かな生態系が蘇りました。その後、アメリカザリガニが増加したため、捕獲用のわなを工夫して仕掛けて密度を減らしています。駆除作業は継続しないと再び繁殖してしまうため、捕獲の効率化や経費削減、食用メニュー開発など、持続可能な活動モデルを全国に広げて生物多様性を守っていきたいと高橋さんは報告しました。
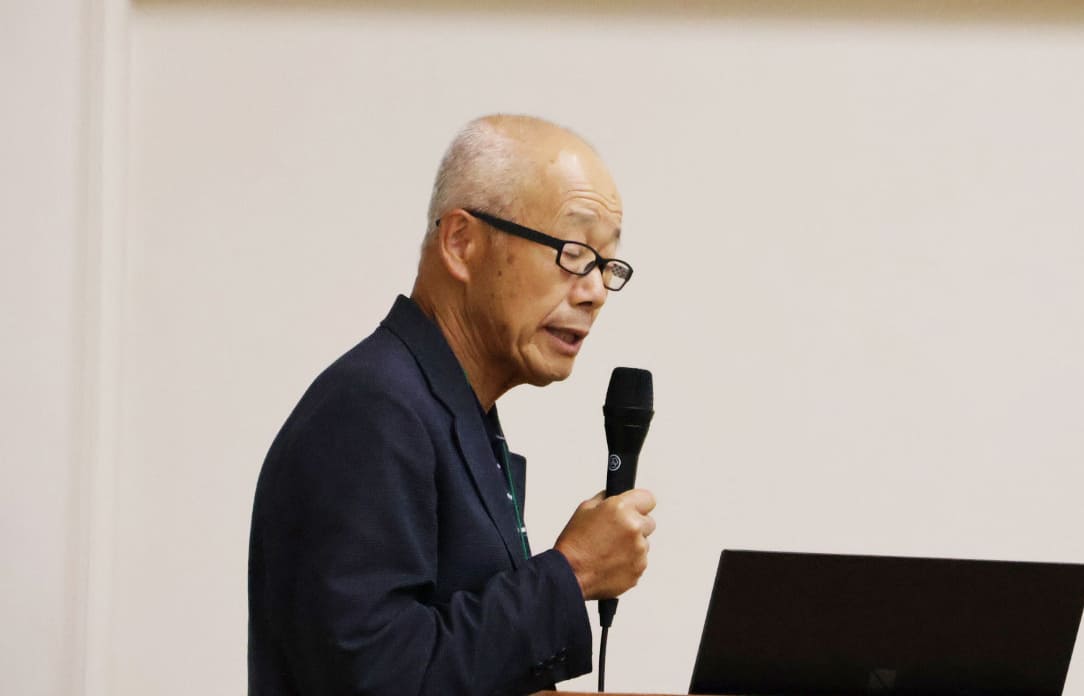
~日本(徳島県阿南市)~
生物多様性戦略で地域を再生
阿南市は豊かな自然を活かして地域の価値を高める「生物多様性あなん戦略」を策定し、生物多様性ホットスポット6か所を選定。市民ボランティアによる生態調査や森林整備を行うと同時に、行政と市民がともに環境教育を行っています。地域の自然の良さを認識するようになり、宮内地区の田んぼでは絶滅危惧種保護の資金調達に近隣の企業も巻き込んで官民協働の活動となりました。地域戦略により街が活性化し、今後は一次産業を巻き込んで経済を回すことが目標です。

田んぼを中心に里地・里山を守る国内外の取り組みが共有されました。湿地の素晴らしさを学び、多くの関係者が積極的に情報を共有し連携することで生物多様性の保護につながっています。
Table Vol.518(2025年10月)


