私たちの生活の中で便利に使われてきた化学物質PFAS(ピーファス)。水や土壌に蓄積し、農作物に移行する可能性があり、農業の現場でもその影響が懸念されています。2025年3月16日、コープ自然派兵庫が参画する西日本アグロエコロジー協会はPFAS研究の第一人者である京都大学大学院(当時)の原田浩二さんを招き、この問題を知ることから始めました。

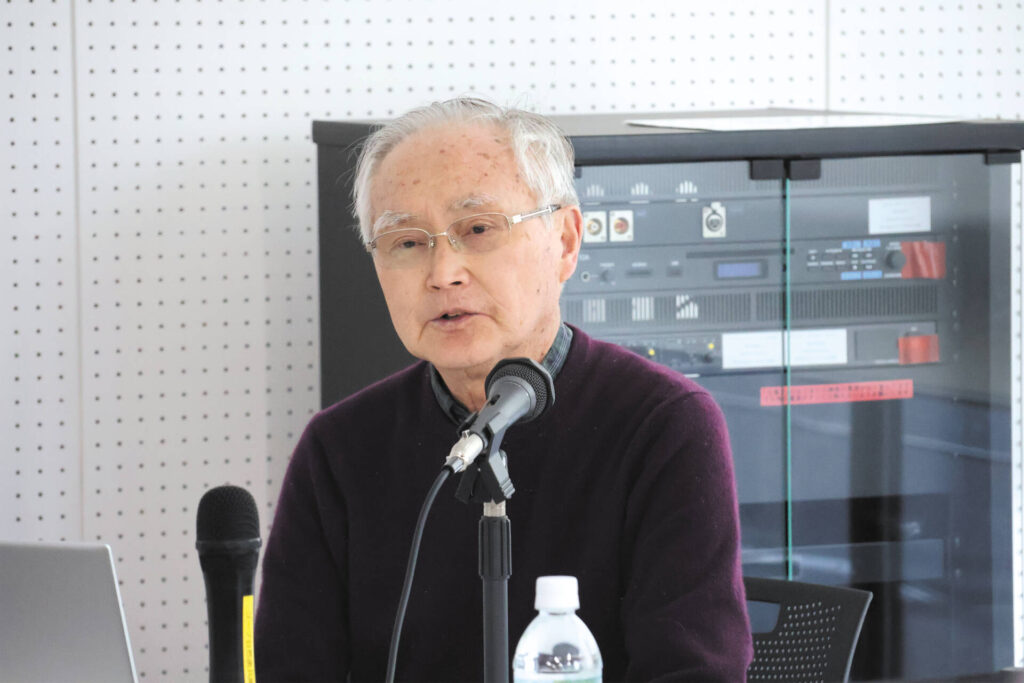
を拠点に農業と生態系共生のアグロエコロジーを推進するNPOです。
永遠の化学物質「PFAS」
PFASは「有機フッ素化合物」のうち結合するフッ素が多いものの総称で、水や油をはじく性質を活かし、フライパンのコーティングやハンバーガーの包装紙、防水スプレー、空港や軍事基地で使われる泡消火剤など幅広く使われてきました。便利な素材である一方で、PFASは自然界でほとんど分解されず「永遠の化学物質」と呼ばれています。水に溶けやすく体内にも蓄積しやすい性質を持つため、世界中で健康や環境への悪影響が注視されています。
世界で始まったPFAS規制
PFASが問題視されるようになったのは1990年代。その後2000年以降アメリカで飲み水や血液からPFASが検出され、肝機能の異常や甲状腺ホルモンの乱れ、低体重出生などとの関連が指摘され始めました。大手化学メーカーの3M社はPFASの一種であるPFOS、PFOAのリスクを認識し、2000年に自主的に製造を中止。2007年にはアメリカ環境保護庁(EPA)が、フッ素樹脂メーカーのデュポン社や日本のダイキン工業に対して環境へのPFASの排出抑制を指導するなど、対策を開始しました。2009年、ストックホルム条約によりPFOSやPFOAなどの新規製造や輸入が国際的に原則禁止になり、PFASに対する世界の意識は確実に変わっていきました。
日本各地で確認されるPFAS汚染
日本でもPFASの存在は明らかになっています。2002年、京都大学が全国の河川を調査した結果、多摩川や大阪国際空港周辺、淀川水系などから高濃度のPFASが検出されました。2020年には、ようやく国が水道水や地下水に対してPFAS濃度の暫定目安( 50ナノグラム/L)を設定しましたが、これを超える地点は2020年で少なくとも全国1都2府10県、計37地点にのぼります。特に注目されるのは、地下水や湧き水に含まれるPFASが、生活用水や農業用水として使われることで、飲み水のほか農地や作物にも影響を与える可能性があるという点です。沖縄県では、湧き水を利用して育てた田芋からPFASの移行が一定程度確認されました。PFASは一度環境に放出されると分解されにくく、長く土壌に残る性質があります。土壌中のPFAS濃度が自然に半減するには約10年かかるとされ、農地への影響も長期にわたる恐れがあります。
PFAS規制と取り組み
欧州では魚や肉など動物性食品を対象に濃度の目安を設ける動きが進んでいます。アメリカでも「スーパーファンド法」によって、土壌汚染の責任と除去を明確にする取り組みが始まりました。現時点では日本にPFASに関する農産物の基準はありませんが、2024年、日本でも環境省が各自治体に土壌汚染調査の方法を示し、全国で対応が始まっています。岡山県吉備中央町では汚染が明らかになったことで、公費による血液検査や健康診断が行われ、住民の健康を守る取り組みが進み始めています。
「知る」「選ぶ」から変えていく
PFASはとても身近な問題です。メーカーの排水や産業廃棄物、また私たちが使う製品も原因となり、川や海、土壌を汚染し、いずれ飲み水となって私たちの体に戻ってきます。「まずは、自分が飲んでいる水を知ること。それが第一歩です」と、原田さんは話します。一部ではありますが、PFASフリーの製品を開発する会社もあります。PFASは個人で完全に避けることは難しいかもしれませんが、「知ること」は誰にでもできます。同時に、一人ひとりが「何を選ぶか」で変えていける問題でもあります。
Table Vol.515(2025年7月)


