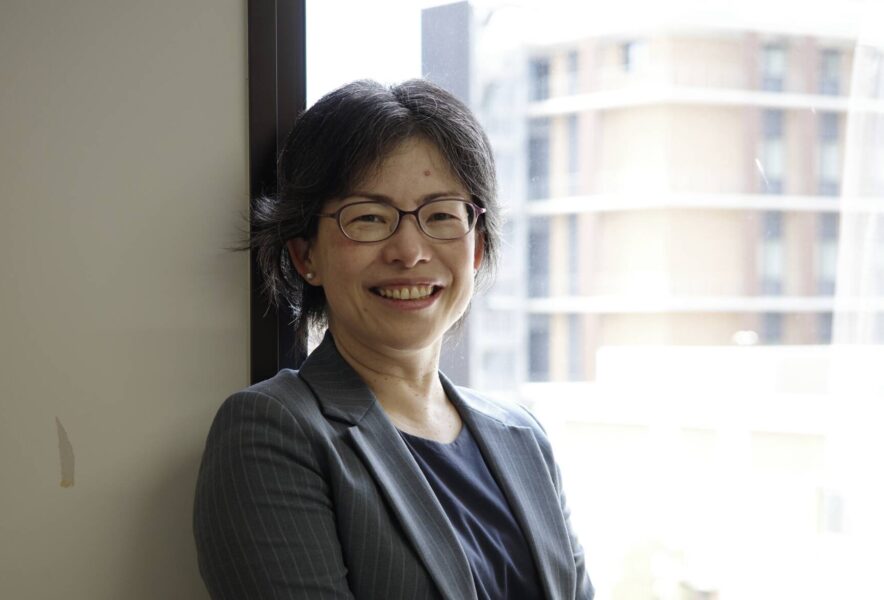豊かなはずの世界で「生きづらい」のはなぜなのでしょうか。食べものから資本主義経済のカラクリを解き明かし、そこから抜け出すためのヒントを平賀緑さんに聞きました。
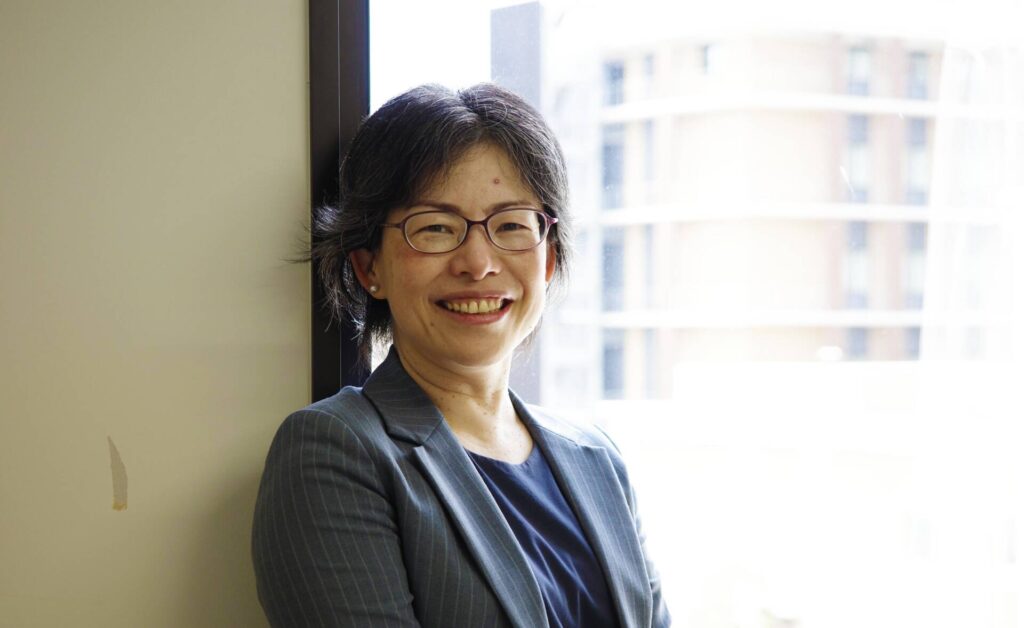
平賀 緑| HIRAGA Midori 広島県出身。1994年に国際基督教大学卒業後、香港中文大学へ留学。2011年に大学院へ移り、ロンドン市立大学修士(食料栄養政策)、京都大学博士(経済学)を取得。植物油を中心に食と資本主義の関係を研究している。主な著書に、『食べものから学ぶ現代社会』、『食べものから学ぶ世界史』(ともに岩波ジュニア新書)、『植物油の政治経済学―大豆と油から考える資本主義的食料システム』(昭和堂)。
食べものから考える資本主義経済
経済学の理論とリアルな社会のズレ
いま、グローバルな農業・食料システムが地球を壊し続けているように見えます。もともと私は香港で新聞記者や国際金融センターでの仕事をしていました。その後、有機菜園で鶏や鴨を育てて食べるというような「命を食す」自給的な生活をした後に、大学院にすすんで経済学の世界に入ると、その理論とリアルな社会とのズレを感じ、現代社会の経済のカラクリを考え始めました。
食べものに関心を持った原点のひとつには、小学生のころに見た飢えた子どもの写真があります。食料の生産量は増えたのに食べられない人も増えたのはなぜなのか。いまの世界経済なら120億人を養うことのできる食料があるというのに10億人近い人が飢えて、他方では十数億人が食べ過ぎて不健康になり、しかも貧しい人ほど肥満になりやすい構造があります。食料を分配すれば良いという話ではなく、そもそも生産しているモノや目的からずれている、もっと大きな政治経済の問題があります。
「食べもの」から「商品」に
資本主義経済は、さまざまなものを商品に変えてきました。産業革命が始まる前は、世界のほとんどの人が生産者であり消費者でした。ところが、それまで農村で自分たちの食べものを自分たちで賄っていた人たちが町に出て、お金のために働くようになった。工場で働く労働者は自分で食べものをつくれないので、そこに市場ができ、その人たちの胃袋を満たすための食料供給システムが形成されていった。しかもそれが利潤を求め続ける資本主義経済に組み込まれ、食べるためのモノが、売って儲けるためにつくる「商品」になった。そこではモノとしての「使用価値」よりも、市場で売れる「交換価値」の方が重視され、競争に負けないために大量生産・大量消費し続けることで経済成長を支える。やがてグローバリゼーションで企業は生産も市場も世界に展開し、さらには経済の「金融化」や公共セクター、データなどへと新たな市場を求めて広がっています。
農家が一番飢えている
現在の農業・食料システムは、この資本主義経済に組み込まれた「資本主義的食料システム(Capitalist Food System)」なのだという認識が重要だと思っています。この仕組みの中では、農業も1 つの産業として売れる商品作物をつくり経営を成り立たせなくてはならない。その農産物を原料に加工食品を製造する食品産業、さらには外食産業、流通・小売業、商社・金融業など、食と農に関わるさまざまな産業が発展してきました。そこに関わるすべての事業体が多かれ少なかれ利益を出して競争し続ける食料システムのなかで、農産物の価格が低迷し、農産物が安すぎるため食料を作っている生産者が一番飢えるという問題が世界的に起きている。
しかも、食べものや農業は確かに自然の恵みであり、命の糧ではあるのですが、今では温室効果ガスの4分の1は食べもの関係から排出されていたり、食生活由来の不健康が大勢の寿命を縮めていたりと、現在の農業・食料システムはまるで人も地球も壊しているような状況です。
現代社会の金融化
食や農も金融資産に
いまや農地も食料の価格も短期的にお金を増やすための投機の対象となり、マネーゲームの駒になっています。すでに現在の資本主義経済は行き詰まり、儲けられる投資先が少なくなくなっている。他方、世界の金融資産は増え続け、さらに運用して増やすためにとにかく儲かりそうなところに流し続けるしかない。そんなマネーゲームに農地や食料の価格も組み込まれています。とくに戦争やパンデミックなどで社会が先行き不安になると、食や農が注目されるそうです。例えば、戦争によってウクライナから小麦が輸出されず供給量が減ったため小麦の価格が高騰したと説明されていますが、これも実際の需給関係より、これから小麦の価格が上がるだろうから儲けよう!という投機的な動機の方が強いと思われます。なぜなら、すでに輸入されていた小麦や倉庫に入った小麦が消えたわけでもないのに、しかも開戦までにウクライナからの小麦輸出シーズンは終わっていたというのに、開戦の直後に価格が高騰した。逆に、実際に戦闘で生産や輸送に問題が出てきそうな半年くらい後には、小麦先物価格は侵攻前の水準に戻ったほどです。現在、小麦の価格を定めるシカゴなどの商品取引所で小麦の先物取引をしている9割以上は農業にも食品にもまったく関係のない機関投資家たちといわれています。
また、現在、米国で最も農地を持っている個人はビル・ゲイツだそうです。マイクロソフトの創業者が農業を始めるというわけではなく、今後農地の価格が上がるだろうと見込んで金融資産の一環として農地をポートフォリオに組み込んでいるのでしょう。他にも主に先進国の資本が、主に途上国の農地を大規模に買い占めている現象も、食料を確保するというより、金融資産的な目的が強いと思われます。

経済学が見落としてきたもの
経済成長の落とし穴
そもそも資本主義経済というものは、人の健康や生活や自然など、お金が関わらない領域を削り取り、それによって企業の利潤や国のGDP(国内総生産)などお金で計算できる部分を増やす仕組みです。そのため、食品を過剰に生産してムダにすればするほどGDPがアップし、多くの人が食べ過ぎて不健康になって医者にかかればGDPアップするなど、人や地球が不健康になればなるほど「経済成長」していることになるおかしなシステムです。
常に成長するためにどこかを搾り取るカラクリのなかで、搾り取られた人や自然がボロボロになるのは「資本主義的食料システム」としては当然との見方もあります。まずはその仕組みを理解する必要があるでしょう。
GDPに含まれない部分に注目
私はこれまでの主流派経済学が無視してきた部分に注目したいと思っています。例えば、いまだ食関係に多い女性の無償労働について。『アダム・スミスの夕食を作ったのは誰か?(カトリーン・キラス・マルサル著)』という本が、経済学の父といわれるアダム・スミスは、肉屋もパン屋も善意ではなく自分の利益を追求することで経済が回り肉やパンが供給されることを説いたけれども、自分の食事を作ってくれた母親の愛情に基づく無償労働は無視していたことを指摘しています。食べもの関係では、いまだに市場を介さない家族のために生産する小農や、遠くまで出荷しない小規模生産者が、じつは世界人口の7割の食を支え、その多くを女性が担っているといわれています。近代的な大規模な農業は、じつは3割程度しか人の胃袋を満たしていないことになります。
他にも、「コモンズとしての食」が見直されていたり、生協運動を発展させたような「社会的連帯経済」が議論され直したりしています。また、宇沢弘文さんが提唱した「社会的共通資本」としての食も考え直したいと目指しています。
現在の経済学の課題は成長より「格差」
資本主義経済のカラクリが生み出す「格差」
ポスト新自由主義の経済学教育に取り組む国際プロジェクト(CORE Econ)によると、経済学が取り組むべき最大の課題は、すでに経済成長ではなく「格差」だそうです。
経済的な格差だけでなく、食べものの分野にも、食べられる人と食べられない人の、食べられるモノが違ってくる「食の格差」が生まれています。健康な食生活はまるで贅沢になりつつあり、日本でも「食べられない」子どもたちが増えていて、1人あたりの1ヶ月の食費が1万円以下の家庭が調査対象の4割という状況になっているそうです。
ワンオペ育児の厳しい実態
とくに(多くは母親だけの)ひとり親と複数の子どもの家庭では、経済的に値上がり続ける食料を買えないという問題もありますが、加えて、時間的にも精神的にも追い詰められている現状があります。たとえコメや大根が無料で玄関まで届けられたとしても、安い食材をうまく使い分けて栄養のある食事をつくるには、かなりの気力やエネルギーが要ります。低賃金な不安定雇用で疲れ果てている人にはまともな食生活を実現することが難しくなっています。
また、食べる側の力も落ちてきていると思います。今どきの学生たちは、生まれたときからペットボトルの水があり、コンビニのおにぎりを買って食べていた世代で、「商品ではない食べもの」が想像できない様子です。食べるスキルとしても、加工食品に慣れていて既製品に抵抗がないし、手軽に惣菜が買える社会で料理しようとする気も薄いでしょう。決して女性だけに台所に戻れというのではなく、老若男女すべての人が自己防衛のために自ら食を選び料理して食べることができるスキルと、それを実現できる「まじめに働けばまともに暮らせる」労働条件が必要と思います。
食料政策として必要な支援は?
このため、誰ひとり取り残さず食を保障するためには、食べる側の現状を正しく把握し必要な支援をすることが重要だと考えます。農家や消費者の努力や理解だけでなく、農と食を動かしている政治経済から見直すことが必要です。農業を存続させるための施策ももちろん重要ですが、産業としての農業が生き延びることと、誰ひとり取り残さずまともな食生活を保障することとは、イコールではないのです。付加価値の高い農産物を推進することは農業政策として真っ当な政策ですが、残念ながらそのような農産物はフードバンクや食べものを必要としている家庭に届くことはまずありません。目的が違うのです。
地域に根ざした食と農と経済へ
菜園から始まる食と農のネットワーク
例えば「フードポリシーカウンセル」で知られるカナダのトロントでは、みんながきちんと食べられるように街全体で都市計画としての食料政策に取り組んでいます。フードバンクだけでなく、誰でも温かい食事が食べられる食堂をつくり、お腹を満たした後で隣接する窓口で雇用やお金、住居や法律的な支援を相談できるようになっています。加えて、自分たちで野菜を育てるコミュニティガーデンがあり、安価な食材から料理を作り上げる料理スクールや安価で利用できるファーマーズマーケットなどもあり、市民が問題を知り声を上げて政策にコミットしていくアドボカシー活動も行われていて、市民の自治、主体性を強めるコミュニティづくりの場にもなっています。日本でも地域全体で行政、企業、市民が総合的に取り組む必要があるのではないでしょうか。
小さく分散して、自主的に動き始める
まずは人も自然も壊してきたカラクリを理解し、その逆に、小さく分散して、自分が主体的に考えてみることから始めてはどうでしょう。それぞれの地域で農の営みと食べる人たちがゆるくつながり、そのコミュニティが持つ価値を育てていく「コモンズ(共)としての食」を再構築する。家庭菜園で自分でつくってみるのも良いし、分かち合える人間関係を築いていく。まともな食を取り戻すためには、食と農だけではなく、政府や企業に任せてきた水道や保険医療や行政サービスなども、ともに取り戻す、「コモンとしての自治」も重要です。
「命の経済」を取り戻す
「命か経済か」ではなく、経世済民としての「命のための経済」を取り戻すために、私たち一人ひとりが主体的にコモンを育てていくことが大切でしょう。まずは今日のご飯から、人も自然も壊さない世界を目指して、一歩動き始めてみてください。私たちの食べもの、生活、命そのものにまで大きな影響を与えている「経済」。でも、人間がつくりあげたシステムなら、その仕組みを変えることもできると思っています。

Table Vol.503(2024年7月)より
一部修正・加筆