2024年10月30日、コープ自然派おおさか(理事会)は、コープ自然派事業連合顧問で日本消費者連盟理事の松尾由美さんを招いて、重イオンビーム育種米について学習会を行いました。
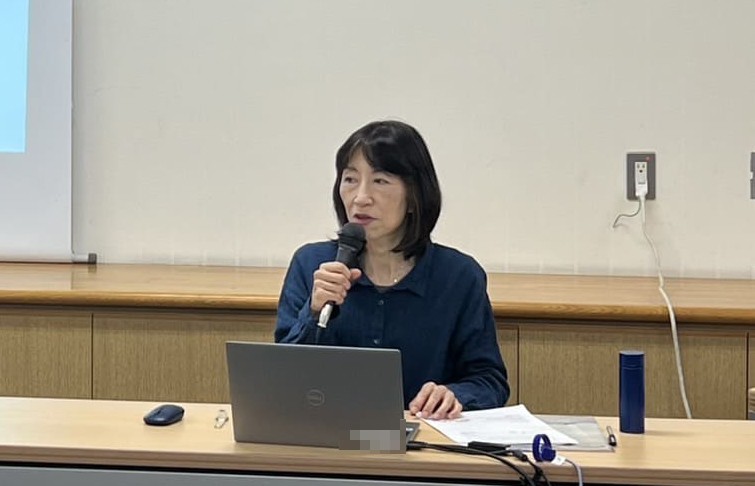
遺伝子操作食品が流通する日本
以前から、遺伝子組み換え(GM)食品やゲノム編集食品は食の安全問題として知られています。GM食品は他の生物の遺伝子を入れる技術で開発した食品です。ゲノム編集も遺伝子を改変する技術で、国内外で研究されていますが、ゲノム編集食品が市場に流通しているのはほぼ日本だけです。目的の遺伝子をピンポイントで壊すことができるといいますが、想定外の遺伝子を壊したり、想定外のタンパク質が生まれる可能性など問題が山積しています。それにもかかわらず、任意の届出だけが求められ、安全性の検査はされず、食品表示の義務もありません。
重イオンビーム育種米とは?
新たに問題となっているのが重イオンビーム育種米。品種改良時に放射線を照射して遺伝子に突然変異を引き起こし、新品種を開発する技術です。以前からガンマ線照射による育種で米、大豆、小麦など500品種以上つくられてきましたが、この技術は安全性が確認されないまま終了しています。重イオンビームはガンマ線の最大1万倍の線エネルギーがあり、その遺伝子を破壊する力は比較にならないほど強いものだそうです。
重イオンビーム育種米の経緯と広がり
明治時代に兵器増産のために鉱山を採掘する際、不要だったカドミウムを環境中に放棄したことで田畑を汚染し、カドミウム腎症やイタイイタイ病の発症に影響しました。このカドミウムの吸収を少なくする米を開発するために重イオンビーム育種の技術を利用したのです。そして国は2025年までに全国の都道府県の3割、2030年までに5割、重イオンビーム育種米の導入を計画しています。
重イオンビームで開発された「コシヒカリ環1号」は、米の生育に必要なマンガンの吸収の低下や、病気にかかりやすくなる、収量が減るといったリスクが生じています。しかし、秋田県では今年から県産「あきたこまち」を(汚染地域だけで生産すれば風評被害になるとして)、コシヒカリ環1号とあきたこまちを掛け合わせた「あきたこまちR」に全量切り替えすることを決定しました。自家採種は禁止されており、種籾の価格が上がったり収量が減る懸念があっても国からの保証はないため、非汚染地域ではメリットがなく、農家の離農につながるのではないかと心配されています。
消費者のリスク
重イオンビーム育種米は、種苗や販売される米には表示がなく、「あきたこまちR」も「あきたこまち」としか書かれないので見分けがつかず、消費者基本法で保障されている「選択する権利」が守られません。今年から全国で販売され学校給食への導入も懸念されます。また国は、有機JAS認定も可能としています。日本は種を守る国際条約に批准しているにもかかわらず国内の種子法は廃止してしまい、種を守る法律が存在していない状態です。
これからの可能性
様々な問題がありますが、Pokkali(インドの在来種の米)が活用できれば問題解決につながる可能性があります。この品種は吸収したカドミウムが根にとどまって米に到達せず、必要なマンガンは取り込むので、遺伝子を操作しない通常の品種改良でカドミウムの吸収が少ない米をつくることができます。
松尾さんは「消費者である私たちにできることは、持続可能な農業やオーガニックにチャレンジする農家を応援したり、ゲノム編集食品や重イオンビーム育種米の表示を求めて、消費者として選択する権利を主張しましょう。1日3回の食事に何を選択するかで世界は変わります」と参加者に呼びかけました。
Table Vol.511(2025年3月)

